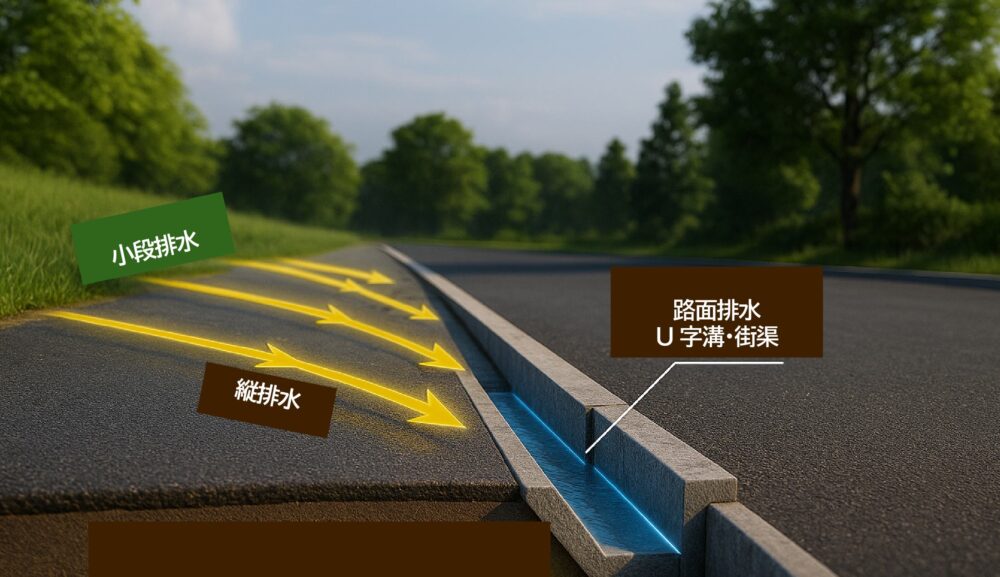■ 土木製図の基礎知識 シリーズ
3.測量座標とは?
5.排水の考え方と高さ・勾配の決め方とは?←このページ
目次
1.排水の考え方
道路や敷地に雨が降ると、そのままでは水たまりや冠水が発生します。
そこで、「雨水を集めて、流し、処理する」仕組みをつくるのが排水計画です。
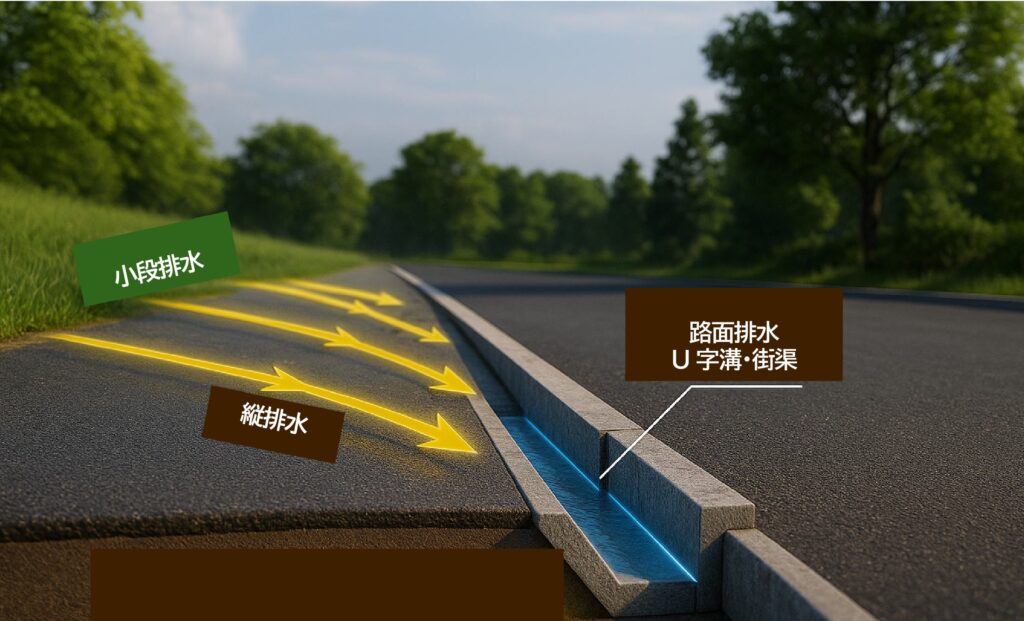
排水の基本的な流れは次のとおりです。
- 路面勾配 → 雨水を片側へ集める
- 側溝(開水路) → 水を受け流す
- 集水桝・排水管 → 下流の幹線へ導く
- 放流 → 河川や下水処理施設へ流す
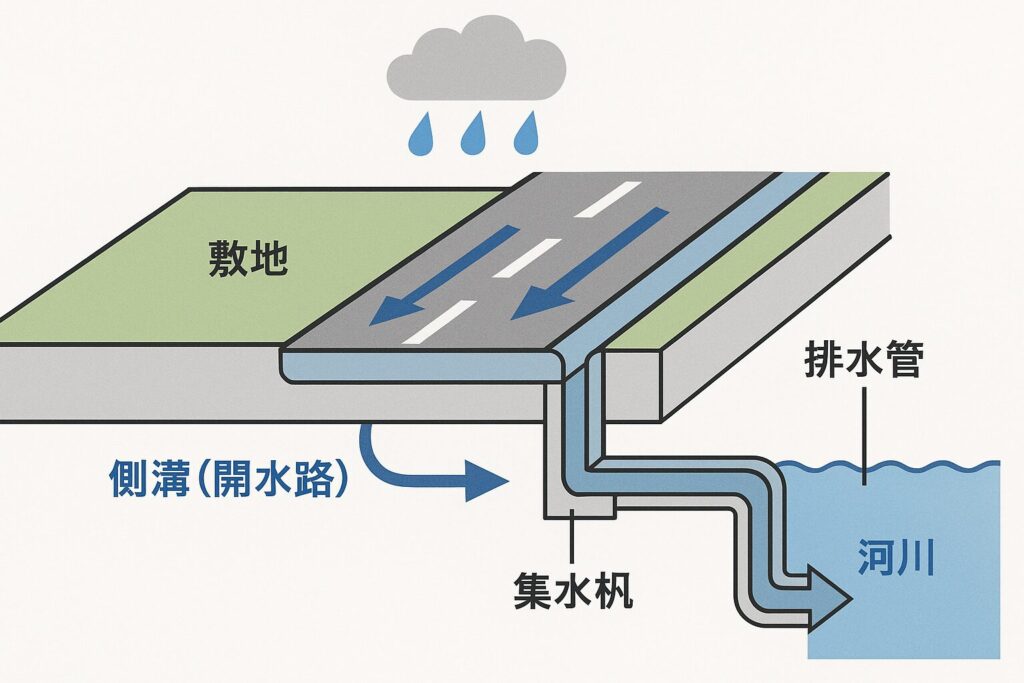
ポイント:「どこに水を集め、どうやって安全に流すか」をあらかじめ設計しておくことです。
2.高さと勾配の基本
1. 高さの基礎用語
- 地盤高(GL):道路や敷地の表面の高さ
- 管頂(クラウン):排水管の上端
- 管底(インバート):排水管の下端(実際に水が流れる高さ)
- 土被り:地盤表面から管頂までの覆いの厚さ
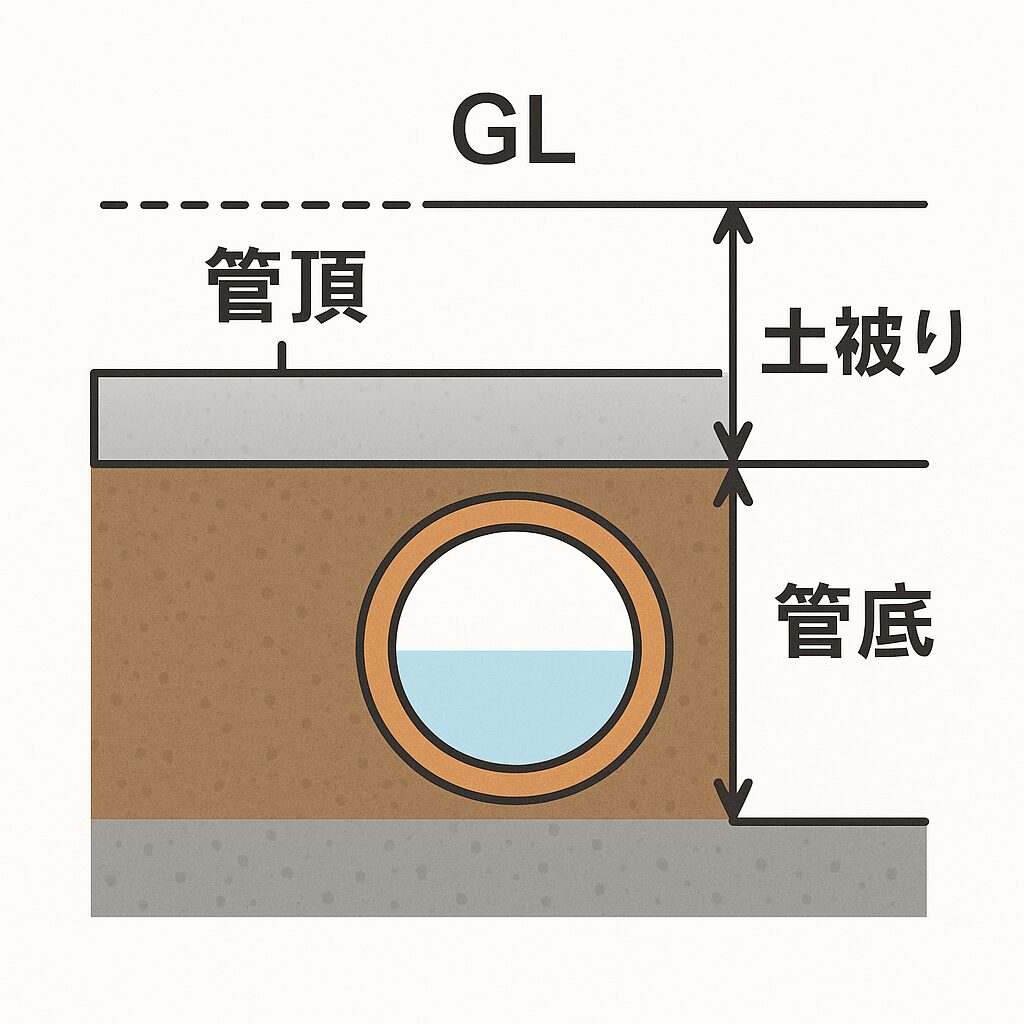
2. 勾配の考え方
- 勾配は「1/n」で表すことが多く、例えば 1/200 = 0.5%
- 下流の管底は、
上流の管底 − 勾配 × 延長
で計算します。
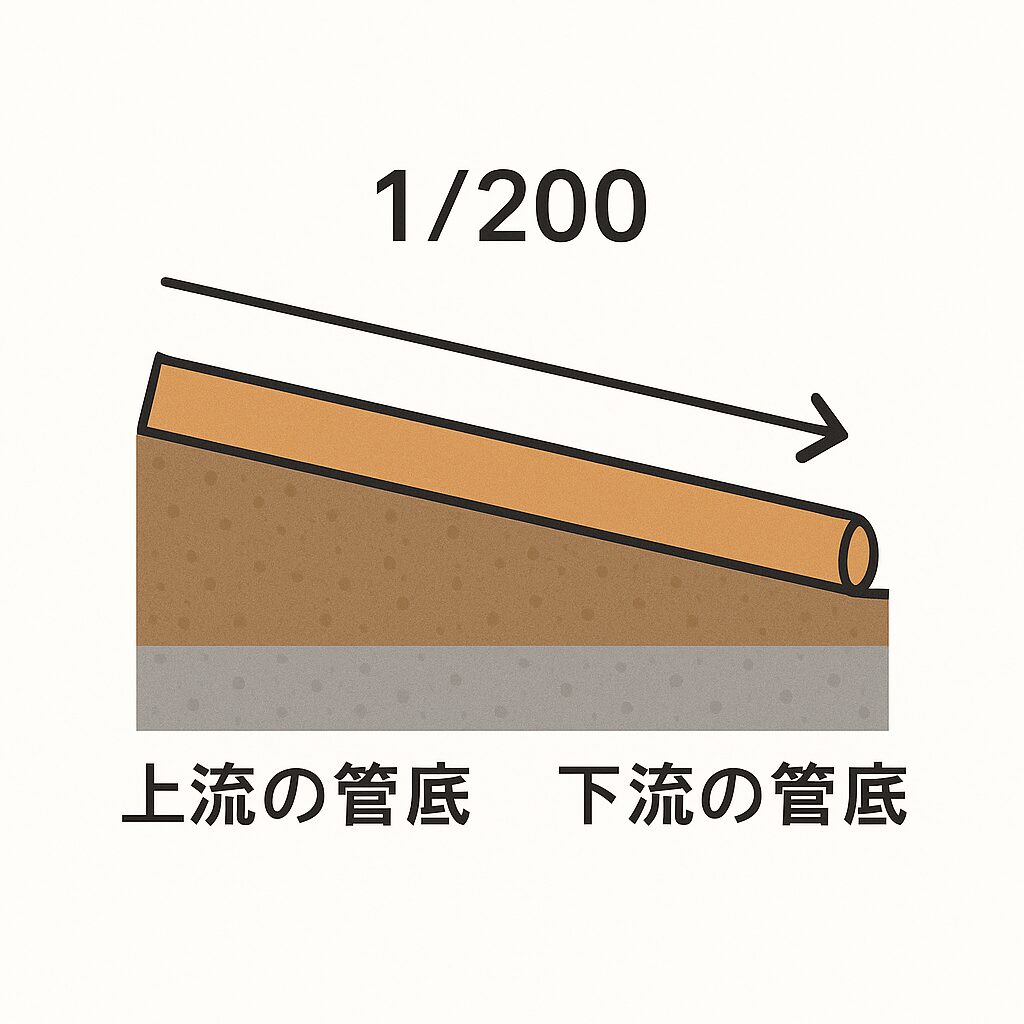
ポイント:これにより、排水管や側溝を「自然に下がっていく流れ」に設計できます。
a) 基本式
【下流の管底高さ=上流の管底高さ−勾配×延長】
- 上流の管底高さ:始点の管の底の高さ
- 勾配:1/n の形(例:1/200 = 0.005 = 0.5%)
- 延長:管の水平距離(m)
b) 具体例
・条件
- 上流の管底高さ(インバート):10.000 m
- 勾配:1/200(= 0.005 = 0.5%)
- 延長:40 m
c) 計算
下流の管底高さ=10.000−(0.005×40)
下流の管底高さ=10.000−0.200
下流の管底高さ=9.800m
d) 解説
- 始点(上流):10.000 m
- 終点(下流):9.800 m
- 40 m の間で 20 cm 下がる → 勾配 1/200 の設計どおり
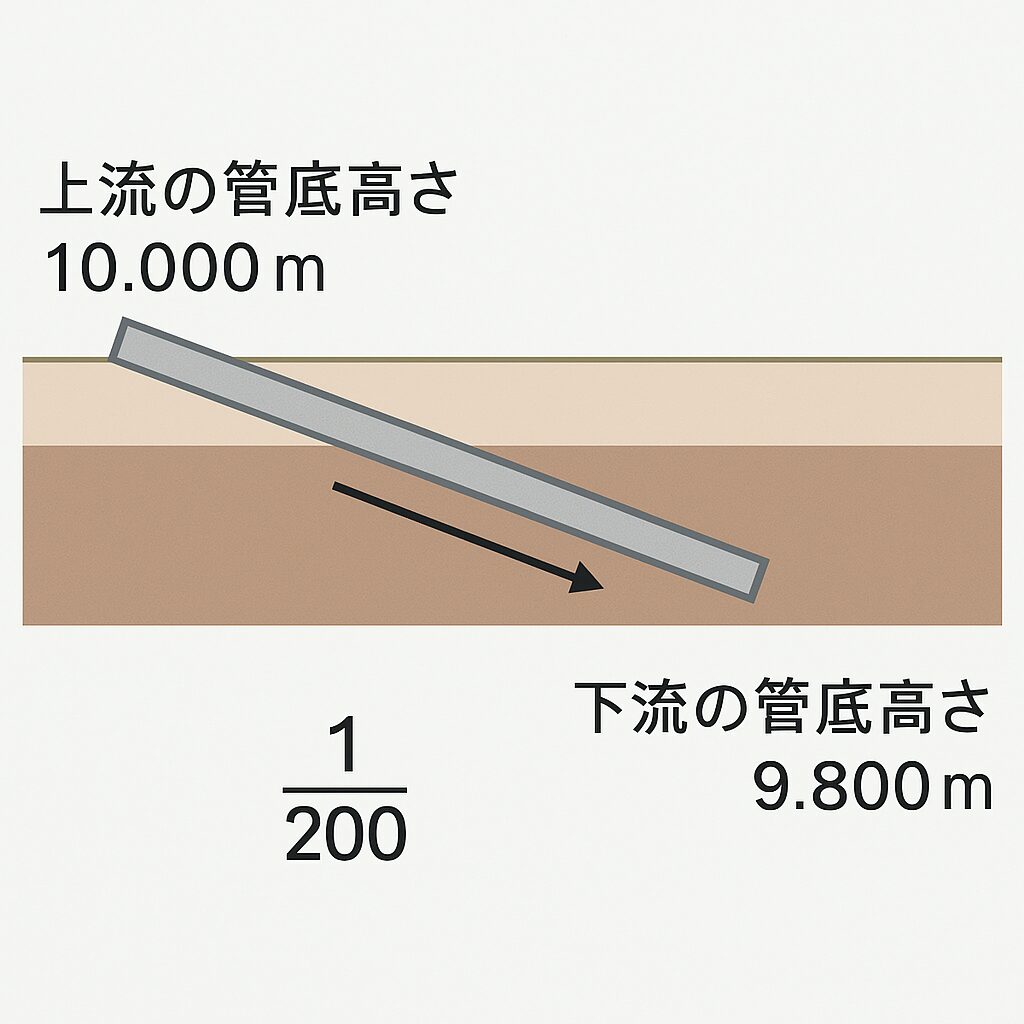
★このようにして「高さが自然に下がっていく」ことで、水が下流へ流れていきます。
3.初心者への目安
- 道路横断勾配:おおよそ 2%
- 側溝の縦断勾配:1/100~1/300 程度
- 排水管の土被り:車道下で 1.0 m 以上が一般的
- 流速の目安:0.6 m/s 以上で堆積を防止
★詳細な数値や設計基準は地域ごとの指針に従いますが、まずは「高さと勾配を意識して水の流れを描く」ことが土木製図の第一歩です。
4.まとめ
- 排水計画は「雨水をどこに流すか」を決めることから始まる
- 側溝や排水管の高さと勾配を正しく決めることが重要
- 初心者はまず「地盤高」「管底」「勾配」の関係を図で理解するのが近道
上記の【PDF資料】がダウンロードできます。『排水の考え方と高さ・鋼材の決め方』
5.排水溝(自由勾配側溝)の工事風景







Youtube動画では、AutoCADで勾配ある線分を描き方を解説しています
<実践で学びたい方へ>
測量座標や縮尺の知識を、実際の図面作成に活かす方法は「AutoCAD土木コース」で学べます。
土木初心者からでも安心してスタートできるカリキュラムで、測量座標・縮尺設定・座標変換の基礎をわかるまで徹底解説します。
👉 AutoCAD土木コースの詳細はこちら
<関連記事>
■ 土木製図の基礎(オンライン無料体験) AutoCAD編
AutoCAD土木製図講座をオンラインで無料体験を行っているYoutube動画の一部です。
新入社員研修に最適なCAD入門書 ― 現場実績から生まれた一冊
日本語の理解できる外国人向けに、AutoCADベーシック講座/土木製図講座を行います
AutoCAD 入門書を【外国人実習生向け】に制作します